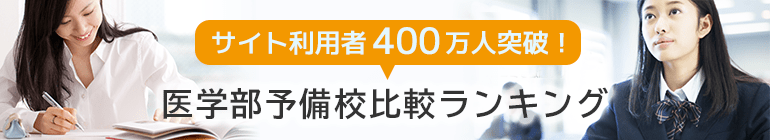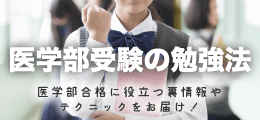医学部医学科の入試難易度は非常に高いですが、その中でも合格しやすい大学を厳選して紹介。
医学部医学科は人気が高く、偏差値・難易度は非常に高いのが特徴。
上位医学部と底辺医学部の難易度の差は他学部に比べてそこまで大きな開きがありません。
それでも合格しやすい難易度の下がる医学部は誰でも知りたいところ。
そこで今回は国公立および私立の医学部入試で合格しやすい大学があるのかについてまとめています。
国公立大学医学部医学科で難易度が下がる大学

まずは国公立大学医学部医学科。
学費が6年総額350万円程度と安いことから受験生にも非常人気が高く、底辺医学部でも東大他学部に合格できる偏差値が要求されます。
そんな国公立大学医学部医学科の中で難易度が下がる傾向を確認していきましょう。
地方の新設医科大学
国公立大学医学部の場合、旧帝大学、旧制医科大学、旧制学専門学校、新設医科大学と医学部が設置された順でヒエラルキー(序列)が形成されており、偏差値や難易度に大きく影響されています。
したがって、地方の大学でも旧制医科大学(熊本大学・長崎大学・岡山大学・新潟大学・金沢大学)だと、他の地域と比較して難易度が高め。
そこでおすすめとなるのが、地方の新設医科大学です。
新設医科大学でも都市部にキャンパスがある国公立大学医学部は受験生の通いやすさや、充実した学生生活が送れることから難易度は高まります。
したがって、キャンパスまでの通学が不便な辺境の地に医学部が設置されている地方国公立大学で、新設医科大学と歴史の浅い大学を目指すと合格しやすいかもしれません。
入試科目の負担が少ない医学部
国公立大学医学部の場合、共通テスト(センター試験)の受験が必須で国語や社会といった文系科目も必須です。
しかし、二次試験は国公立大学によって異なっており、入試科目が全てが一緒ではありません。
かつては面接試験がない医学部もありましたが、2020年に九州大学は面接試験を導入して今では全医学部で実施されています。
ただし、二次試験の入試科目が少ない医学部を選べば、共通テスト後の二次試験対策の負担が軽減できるので、難易度が下がるかもしれません。
昔は信州大学のように数学・小論文・面接だけのような負担の少ない医学部もありました。
現在は二次試験の入試科目は全国の医学部で増加傾向で、最低でも英語と数学は必須ですが、理科科目がない医学部は穴場かもしれません。
特に理科が苦手な受験生にとっては、難易度が下がると言っていいでしょう。
ここからは、二次試験で
- 理科がない
- 理科1科目の医学部
- 英語がない
- 秋田大学
- 山形大学
- 新潟大学
- 福井大学
- 鳥取大学
- 徳島大学
- 香川大学
- 佐賀大学
- 鹿児島大学
- 琉球大学
医学部を順番に紹介していきます。
前期日程二次試験で理科のない医学部一覧(2023)
| 大学名 | 二次試験 |
|---|---|
| 旭川医科大学 | 英語150点、 数学150点、面接50点 |
| 秋田大学 | 英語100点、 数学100点、面接200点 |
| 島根大学 | 英語200点、 数学200点、面接60点 |
| 徳島大学 | 英語200点、 数学200点、面接 |
| 弘前大学 | 総合問題300点、 面接200点 |
2022年度から宮崎大学医学部が理科二科目を導入したことで、2023年度入試において前期日程二次試験で理科を必要としない国公立の医学部は上記の5校となりました。
2022年度の宮崎大学医学部の理科は非常に難関であったので、これから宮崎大学医学部を狙う医学部受験生は注意が必要です。
これらの上記5大学においては、科目や配点は特に2022年度からの変更はありませんでした。
理科のない国公立医学部は限定的であり、理科がない分合格難易度は下がりますが、志願者の多くが同じように理科がないという理由で受験しにくることから、ひとえに簡単とは言えません。
むしろ理科が苦手な分、英語や面接などで自信を持っている学生が志望する傾向にあるので、そういった科目が得意でない場合は合格難易度がむしろ上がってしまうことに注意してください。
前期日程二次試験で理科1科目の医学部(2023)
| 大学 | 英語 | 数学 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県立医科大学(前期) | 150 | 150 | 150 | 理科は物化生から1科目 |
意外にも、国公立医学部で二次試験に理科が1科目で受験できる大学があります。
ただし英語や数学も含め、問題自体の難易度は単科大学ということもあり比較的難易度は高め
総合的には決して難易度が低い大学とは言えませんが、理科がどうしても苦手で英語や数学が得意だという受験生にとっては合格難易度が大きく下がるため、おすすめです。
前期日程二次試験で英語のない医学部もおすすめ(2023)
| 群馬大学 | 数学150点、理科(物化)150点、小論文(理系と英語の能力を問うことがある)150点、面接 |
|---|
共通テストでの英語の点数は評価の対象となりますが、群馬大学では二次試験に英語が課されていません。
小論文で英文が課されうるとはいえ、英語長文が苦手な受験生にとっては、少し難易度が下がるかもしれませんね。
なお、秋田大学と愛媛大学も入試科目としての英語は課されていません。
ただ、総合問題として出題される内容に英語が含まれるので結果として英語の入試対策は必要です。
二次試験で学部共通問題が出題される大学
一部の国公立大学のみに見られるのが、この「学部共通問題」。
多くの大学では、医学部独自の問題、難易度の高い問題が出題されますが、他学部と共通の問題を出題する大学もあるのです。
他学部と共通の問題となると、それだけ問題の難易度は平坦化し、場合によっては共通テスト(旧センター試験)レベルの内容であることも珍しくありません。
もちろんライバルは高得点を取ってくるため、「高得点が必須な共通問題」と「難しい学部独自問題」のどちらが難易度が低いかは議論が分かれるところですが、少なくとも受験対策として、問題自体の難易度が低い学部共通問題の対策の方がしやすいことは間違いありません。
学部共通問題を採用している国公立医学部は意外にも多いので、ここではその中でも比較的難易度が低いとされる大学をご紹介します。
難易度が低いといっても受験生本人と問題との相性は大事なので、検討する際にはぜひ実際に問題を解いてみて選んでみてください
私立大学医学部医学科で難易度が下がる大学

私立大学医学部医学科の一般入試は国公立とはまた違う傾向があります。
それではどんな点で難易度が下がる傾向にあるのかを確認していきましょう。
学費が高額な大学は一般的に偏差値が下がる
私立大学医学部の場合は、ヒエラルキーよりも学費で難易度が大きく影響する傾向にあります。
やはり、私立大学医学部の学費は高額になるため、入学できる医学部は世帯によって大きく異なりがち。
そこで、学費の安い私立大学医学部は多くの受験生が目指せる大学として人気が集まり、毎年高い難易度を誇っています。
特に6年総額2000万円台前半の私立大学医学部には国公立の併願組も多く受験してくるため、偏差値は非常に高いです。
逆に学費が3500万円以上から4000万円超の私立となると経済的に厳しい受験生も多く敬遠する傾向にあるため、難易度は下がる傾向に。
したがって、経済的に問題がなければ、合格できる可能性は高まるということです。
2021年度の入試で言えば、東京女子医科大学が学費1200万円値上げすることを発表したことを受け、志願者が1362名(2020年)から945名と大幅に減少し穴場となりました。
また、東京女子医科大学の学費値上げ前まで最高額だった川崎医科大学は偏差値は最も低い医学部として有名です。
2023年私立医学部学費ランキング(低い順)トップ5
| 大学名 | 学費(6年間総額) |
|---|---|
| 国際医療福祉大学 | 1850万円 |
| 順天堂大学 | 2080万円 |
| 関西医科大学 | 2100万円 |
| 慶應義塾大学 | 2206万円 |
| 日本医科大学 | 2298万円 |
2023年度入試から関西医科大学が学費を大幅に値下げすることを発表しました。
2022年度までは6年間の総額で2770万円だったのが、2023年度以降は2100万円となり、私立医学部の中では国際医療福祉大学と順天堂大学に次いで3番目に安い医学部に躍り出ました。
2008年に順天堂大学が学費の大幅に値下げをしたことで人気が上がり、合格難易度が急上昇したように、関西医科大学でも相当の人気を得て合格難易度は跳ね上がるであろうと思われます。
また関西医科大学の場合はこれまでも比較的学費は安く、大阪市周辺といった立地にあることから人気自体は高かったのですが、それでも大阪という立地上、関東や東北地方からの受験者はやや抑えめだったという事情があります。
しかし全国ランキングTOP3にまで学費が安くなってしまうと、住んでいる地方を問わず、全国から遠征してでも受験しに来る学生が増えると予想されます。
したがって関東圏やその他地域の優秀な学生が一気に志望校にすると予想されているので難易度の急激な上昇に注意が必要です。
また、上記の表にはランクインしませんでしたが、関西医科大学と並んで関西の私立医学部ツートップの一つである大阪医科薬科大学も2023年度の入試から学費を大幅に値下げし2841万円にまで値下げをしたので、こちらも難易度が上がると予想されます。
2023年度私立医学部学費ランキング(高い順)トップ5
| 大学名 | 学費(6年間総額) |
|---|---|
| 川崎医科大学 | 4736万円 |
| 東京女子医科大学 | 4621万円 |
| 金沢医科大学 | 4054万円 |
| 埼玉医科大学 | 3957万円 |
| 北里大学 | 3952万円 |
2022年度から東京女子医科大学では学費を大幅に値上げしたため、2023年度入試の段階では私立医学部の中で川崎医科大学に次ぐ学費が最高額な医学部となっています。
東京女子医科大学はコロナ禍によって病院経営の赤字が拡大したために、仕方なく学費の大幅値上げに踏み切ったという経緯があります。
そんな東京女子医科大学の学費はなんと6年間総額で4621万円と、控えめに言っても一般家庭ではとても払える額ではありません。
そのため、2022年度からは前年までと比べて大幅に志願者数が減ったため、ある意味競争倍率は減り、狙い目の医学部となりました。
一般に私立医学部は学費を値下げすると難易度が上がり、値上げすると難易度は下がると言われています。
川崎医科大学医学部は国公立・私立の全医学部の中で最も学費が高く、偏差値も低いことで有名でしたが、東京女子医科大学が同水準の学費になったのでこれら二校の難易度がどう変動していくか注目すべきです。
帝京大学の試験は必須科目は英語だけで最大3回受験できる
帝京大学医学部は学費総額3938万円と高額であるのと、入試制度が他大学と異なることから合格しやすい医学部の1つとして有名です。
入試科目については必須科目は英語だけ。
そして、選択科目の国語・数学・化学・物理・生物の5科目から2科目を選択することになります。
国語で受験できること、そして数学の範囲に数Ⅲが含まれないことから文系出身の受験生にとって難易度が下がることでも人気です。
また、試験日が3日間があり、最大3日受験でき、最も高い日の得点が合否に採用されるため、例え初日で失敗しても挽回可能なのが魅力。
もちろん、制度はライバルもみんな同じなので、合格得点が上がることは珍しいことではありません。
帝京大学を受験するなら3日間挑戦することが合格難易度を下げるためにもおすすめです。
数Ⅲを課さない医学部
数Ⅲを課さない医学部は帝京大学の他に、近畿大学と金沢医科大学(後期)があります。
そして2023年度からは東海大学医学部でも、数学の試験範囲から数Ⅲが削除されました。
東海大学はもとより理科1科目受験が可能なことで有名でしたが、数Ⅲが免除されるということで、さらに理系科目に苦手意識を持っている医学部受験生にとっては合格しやすい展開となっています。
医学部受験における数Ⅲの比重は絶大で、難易度に大きく関わっていると言えます。
そのため、これら数Ⅲを課さない医学部は、数Ⅲが苦手な受験生にとっては比較的難易度が下がるかもしれません。
東海大学は理科1科目で受験可能
私立大学医学部でも帝京大学を除き、理科二科目が必須であることがほとんど。
しかし、東海大学は英語・数学・理科1科目で受験が可能です。
したがって、理科の対策の負担が軽減するため、難易度が下がると感じる受験生もいることでしょう。
ただし、受験生がみんな得意な理科科目で受験してくるため、高得点争いとなり難易度がむしろ上がるという声も聞かれます。
理科2科目の対策しているけれど、1科目しか安定して高得点が取れないという受験生にとってはおすすめになるかもしれません。
さらに前述の通り、東海大学医学部では2023年度より数学の試験範囲から数Ⅲを削除したため、よりいっそう理系科目の負担は軽減されます。
東海大学医学部では文系出身の受験生に対策しやすい環境になっているといえます。
| 一般入試 | 英語100点、数学100点、 理科1科目100点、小論文、面接 |
|---|
特別枠・地域枠は大きく難易度が下がる傾向
意外と知られていないのが、特別枠や地域枠の存在。
2023年度入試の難易度予想の指標としては、前年度である2022年度入試のボーダー偏差値をもとに考えていきます。
例えば、2022年度の福島県立医科大学の前期一般枠のボーダー偏差値は62.5で苦あったのに対し、前期地域枠の偏差値は60.0と一般枠よりもやや低めの数値に。
三重大学でも2022年度入試での前期一般枠のボーダー偏差値は65.0であるのに対し、前期地域枠のボーダー偏差値は62.5と、やはり一般枠よりも地域枠の方が低く出ていることが分かります。
こういった傾向は国公立医学部だけでなく、私立医学部でも2022年度の岩手医科大学の一般枠のボーダー偏差値が62.5だったのに対し、地域枠Cでのボーダー偏差値は少し低くなって60.0でした。(河合塾発表 合格可能性50%偏差値より)
このように医学部受験において、特別枠や地域枠では一般枠よりも難易度が下がる傾向にあります。
もちろん、そもそもの受験資格として「その地域出身者であること」や成績基準、現役のみなどの条件があるため、誰もが受けられる枠ではありません。
しかし、中には弘前大学の青森県定着枠のように、その地域にゆかりのない人でも受験できるものもあります。
特別枠・地域枠のほぼ全てが、「卒業後、その地域で9年以上従事すること」といった条件が課せられます。
この条件こそ、一般枠から難易度が大きく下がる原因ですが、就職先を厭わず医学部にどうしても入りたいという受験生には、地域枠がおすすめです。
その他の医学部受験制度
推薦入試
医学部には、一般入試以外にも推薦入試で入学することも可能です。
他学部で近年増加中のAO入試を導入している医学部も年々増えてきており、北は北大から南は琉球大学まで、国公立大学私立大学ともに受験方式の幅が広がっています。
多くの大学で、推薦入試の出願条件として現役もしくは1浪・2浪までという年齢条件や成績基準を設けていることがあるため注意が必要です。
しかしこの条件を満たす受験生はかなり限られ、全員が実際に推薦入試にエントリーするわけではないため、受験人口は一般入試と比べて大幅に減少しかなり難易度は下がります。
中には推薦入試合格者は地域医療への従事が条件として課されていたりと要項をよく確認する必要がありますが、共通テストで十分な合格点さえ獲得することができれば二次試験をせずに医学部合格が可能であり、かなり穴場の入試方式であると言えます。
学士編入試験
一度4年制大学を卒業し学士課程を修了している医学部再受験生には、学士編入試験がおすすめ。
医学部の学士編入は4月から試験が開始したり、そもそもの情報があまり出回っていないなどのデメリットはありますが、受験人口自体は少なく、社会人としての経歴やこれまでの経験を面接でアピールすることができる点で大きなメリットも。
大学院まで進み研究論文で良い結果を残した方や、企業などで十分な経験を積まれた方にはとてもおすすめです。
なお、学士編入を実施しているのは国公立大学がほとんどですが、私立大学でも3校で実施されています。
受験生によってどのくらい難易度が変わってくるのかは状況によって異なりますが、場合によっては医学部再受験として一般入試にチャレンジするよりも遥かに合格難易度が低いこともあります。
人気急上昇?海外医学部の受験
近年、医学部受験生の中で海外大学医学部への受験を検討する人が増えています。
コロナ禍で2021年入試や2022年度入試では大幅な減少が見込まれていますが、入試に向けて準備している学生は大勢です。
例えば中国の北京大学は世界大学ランキングで上位に君臨する名門大学ですが、医学部7学年中の下4学年には既に各学年で日本人が20名以上在籍しています。
そのほか、東南アジアの大学はもちろん、スェーデンやベルギー、アメリカやカナダなどの世界各国の医学部への受験が可能です。
入試難易度という点では、大幅に上昇してしまう海外大学がほとんど。
しかし、海外では日本と違い大学に入学すること自体は比較的難易度が低いため、特に英語が得意な受験生にとってはかなり難易度がかなり下がることになります。
地域によっては私立医学部に進学するよりも生活費を含めた学費が安くなることもあり、一部の受験生には人気の医学部入試です。
まとめ
以上のように、今回は医学部の中で難易度の下がる大学を国公立・私立に分けて紹介してきました。
ただし、注意しておきたいのは医学部医学科の中で難易度が下がるだけで、大学入試全体を考えれば非常に難易度は高いことには変わりありません。
上記の合格しやすい大学でも甘くみてると不合格は当たり前。
偏差値がクリアしていても、過去問など活用してしっかりと大学別対策を行っておかないと合格できない受験生は毎年日常茶飯事です。
決して甘くみずに徹底的に準備して試験に臨むことが重要です。
当サイトでは、現在医学部予備校の口コミ・体験談を募集しています。医学部志望の受験生に役立つ情報の場として、ぜひご協力お願いいたします。
口コミ投稿はこちら
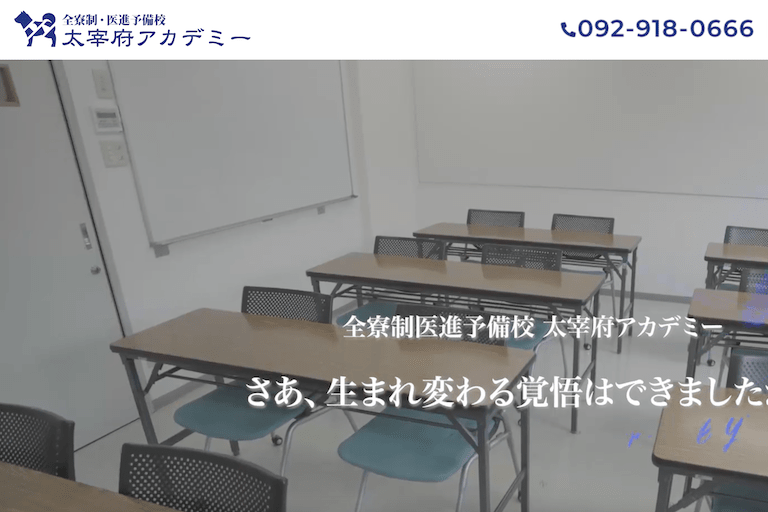
福岡で合格実績豊富な全寮制の医学部予備校

生徒の2人に1人が医学部進学を実現させる実力派予備校